プレゼンテーションの基本構成とオススメフォーマット3選。シーン別のオススメも紹介。
社会人であれば、プレゼンテーションをする機会が訪れることもあるでしょう。
プレゼンテーションをする際には、基本構成やシーン別に使い分けられるフォーマットを活用すると、相手に伝わりやすくなり効果的かもしれません。
プレゼンテーションの基本構成とオススメのフォーマットをご紹介します。
目次
プレゼンテーションの基本構成

プレゼンテーションの基本構成は、次のとおりです。
①序論/イントロダクション
②本論/ボディ
③結論/クロージング
それぞれの段階の役割を解説します。
序論/イントロダクション
「序論/イントロダクション」は、プレゼンテーションの導入にあたり、プレゼンテーションのテーマやプレゼンを行う理由などを話していきます。
具体的には、プレゼンテーションの内容の目次、自己紹介、プレゼンテーションの目的をまとめます。自己紹介で話し手の経歴を示すと、プレゼンテーションの内容に説得力を持たせられるかもしれません。
「序論/イントロダクション」では、聞き手の関心を引くことが大切です。聞き手の関心を引けない場合、その後の内容を集中して聞いてもらえない恐れがあるため、つかみを意識したり、聞き手が興味をそそられるような話をしたりすることが求められます。
本論/ボディ
「本論/ボディ」は、聞き手に伝えたい内容の詳細の部分です。聞き手に内容を簡潔に分かりやすく伝えるために、データやグラフなどの根拠を示しましょう。
文章を目立たせようと多くの色を使った場合、一番注目してほしい箇所を見てもらえない恐れがあるため、色の多用を避けることが望ましいです。
結論/クロージング
「結論/クロージング」は、プレゼンテーションの「まとめ」にあたります。
「本論/ボディ」の要点をまとめたり、今後、聞き手に期待する行動を伝えたりして、内容の振り返りや、聞き手のアクションを促します。また、質疑応答の時間を設けて聞き手の疑問を解消したり、聞き手へお礼を述べたりすることも組み込めるでしょう。
プレゼンテーションの終了を示すスライドは、しばらく表示させておけると考えられるため、聞き手に伝えたい内容を改めてまとめたスライドを用意するなど、最後まで聞き手を意識することが大切です。
オススメのプレゼン構成フォーマット3選

プレゼンテーションには、基本構成以外に、相手に分かりやすく伝えられるオススメの構成フォーマットが3つあります。
構成フォーマットの内容について解説します。
SDS法
SDS(エスディーエス)法とは、「Summary(要点)」「Details(詳細)」「Summary(要点)」の順で相手に伝えるシンプルな構成で、プレゼンテーション以外にニュース番組でも活用されています。
①Summary(要点):文章の概要
②Details(詳細):具体的な内容
③Summary(要点):まとめ
SDS法は、相手の集中力が高い冒頭で要点を話し、詳細を説明するため、相手に内容を理解してもらいやすいです。
また、最後にまとめとして再度要点を話すため、相手の記憶に残りやすいでしょう。
【SDS法の例】
①S(要点):業務効率化のため、顧客管理システムの導入を決定しました。
②D(詳細):顧客情報を紙で扱っていると、多くの顧客情報のなかから必要な情報を探し出すのに時間がかかります。また、ほかのファイルに誤って綴じられ、紛失騒ぎも起きました。
③S(要点):よって、顧客情報をデータで管理できる顧客管理システムを導入することにしました。
PREP法
PREP(プレップ)法とは、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(例)」「Point(結論)」で構成されている文章作成方法です。
①Point(結論):話の結論
②Reason(理由):結論に至った理由の説明
③Example(例):理由を補足する具体例
④Point(結論):まとめとして再度結論を伝える
PREP法は、結論から伝えたり、理由や具体例を提示したりするため、簡潔で説得力のある説明を行えるでしょう。
ビジネスでは、プレゼンテーション以外にも、上司への報告やビジネスメールなど、相手にわかりやすく簡潔に説明しなければいけないシーンが多々あります。PREP法を活用すると、論理的に物事を伝えられるため、相手に「結局何が言いたいの?」と言われることがなくなるかもしれません。
【PREP法の例】
①P(結論):業務効率化のため、顧客管理システムの導入を決定しました。
②R(理由):自社では顧客情報を紙で扱っており、従業員が探し出すのに時間を要したり、ほかのファイルに誤って綴じたりしたため、紙での保存では業務が非効率になると判断したからです。
③E(例):具体的には、従業員が顧客からの問い合わせを受け、顧客情報を確認しようとしたところ、顧客数が多く見つけるのに時間がかかり、お待たせした顧客からお叱りを受けました。また、顧客情報をまとめた紙を違うファイルに綴じたことで、該当の顧客情報が見つからず、紛失騒ぎも起きてしまいました。
④P(結論):そのため、従業員の負担やミスの軽減、顧客サービスの向上の観点から、顧客管理システムの導入によって業務効率化をはかろうと考えました。
■関連記事
PREP法とは?身につけるメリットは?例文やトレーニング法も紹介!
DESC法
DESC(デスク)法とは、「Describe(描写)」「Express(表現)」「Suggest(提案)」「Choose(選択)」で構成された文章作成方法で、相手の気持ちを尊重したプレゼンに活用できます。
①Describe(描写):客観的な事実を描写
②Express(表現):客観的な事実に対する主観を表現
③Suggest(提案):事実の解決法を提案
④Choose(選択):相手が提案を受け入れた場合と受け入れなかった場合の行動を選択
DESC法は、相手に物事を依頼するときなどに、相手の気持ちを尊重しながら自分の意見も伝えられる方法のため、お互いに納得感を得やすいです。
また、客観的な事実から描写することで、相手に伝えたい提案部分の説得力が増すため、問題解決型のプレゼンテーションに適しているといえます。
【DESC法の例】
①D(描写):他社ではペーパーレス化が進んでおり、顧客情報を紙ではなく電子データとして保存している企業が多いです。
②E(表現):御社は顧客情報を紙で保存していますが、探し出すのに時間がかかったり、紛失のリスクもあったりするため、効率的な保存方法とはいえないでしょう。
③S(提案):そこで、顧客管理システムを導入してはいかがでしょうか?顧客管理システムを導入すれば、ペーパーレス化できるだけでなく、業務効率化もはかれます。
④C(選択):
・(相手が提案を受け入れた場合)では、まずは御社に合った顧客管理システムを検討していきましょう。
・(相手が提案を受け入れなかった場合)では、顧客管理システムのパンフレットを置いていきますので、お手すきの際にご覧いただけますでしょうか?
シーン別の構成フォーマットの使い分け

構成フォーマットは、シーンに応じて使い分けるとより効果的でしょう。
シーン別にオススメの構成フォーマットをご紹介します。
社内プレゼン向けの構成
「報告」が主となるケースが多い社内でのプレゼンテーションの場合は、PREP法やSDS法を活用しましょう。PREP法とSDS法は、ともに結論から述べる方法のため、相手にわかりやすく簡潔に内容を説明できます。
特に、プレゼンテーションの時間があまり設けられていない場合はSDS法、時間があり、相手が論理的な説明を求める場合はPREP法を使うことをオススメします。
社外(営業)プレゼン向けの構成
社外(営業)でのプレゼンテーションの場合は、SDS法が適しているでしょう。SDS法は、要点を二度伝えるため相手の記憶に残りやすいです。また、プレゼンテーション時間も限られている可能性が高いため、シンプルな構成であるSDS法をオススメします。
一方で、相手が抱えている問題が明確な場合は、DESC法も活用できます。相手の気持ちを尊重しつつ、解決策を提案していきましょう。
効果的なプレゼン構成を意識して失敗しないプレゼンを

プレゼンテーションには基本的な構成がありますが、SDS法やPREP法、DESC法などの構成フォーマットもあるため、状況に応じて使い分けると効果的でしょう。
構成に慣れるまでは大変かもしれませんが、普段のビジネスシーンから意識して活用すると、コツが掴め、失敗しないプレゼンテーションにつなげられるかもしれませんよ。

記事執筆や校正など文字に関わる仕事を幅広く行う元金融業のフリーライター。静岡県在住だけど岐阜県も大好き。戦国武将の推しは斎藤道三。(ブログ:https://enmojilaboblog.com/)

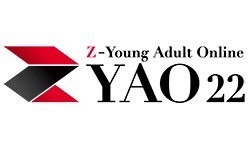
.jpg)
-1.jpg)
_クレジット追加.jpg)
.jpg)




