壁紙ブランド「WhO(フー)」、全国各地から参加したクリエイターによる上士幌町を表現する壁紙7点を発表
自治体と取り組む4泊5日の滞在型ワークショップより誕生
2025/8/5
壁紙ブランド「WhO(フー)」
インテリア内装材·壁紙ブランド「WhO(フー)」(野原グループ株式会社 本社:東京都新宿区 代表取締役社長:野原弘輔)は、北海道上士幌町(以下、上士幌町)と、一般社団法人ねづく(所在地:北海道河東郡上士幌町 代表理事:辻彩香)と共催し、関係人口の拡大とクリエイティブなまちづくりを目的に4泊5日間の上士幌町での滞在を通じて壁紙のデザインを制作する「かみしほろ デザインワークショップ」を開催。本イベントのグランプリ作品及び参加者による作品計7点を8月5日に発表いたします。
「かみしほろデザインワークショップ」について
2025年1月29日~2月2日の5日間、全国各地から肩書も年齢もさまざまなクリエイター8名が北海道上士幌町に集まり、「にっぽうの家」にて共同で暮らす形で滞在。役場の方や町で生まれ育った方から歴史や特色などを伺う座学に始まり、凍結した湖面の上に雪が降り積もる広大な糠平エリアの散策や、日本で初めて気球の大会を開催した点にちなみ気球に乗る体験などさまざまなアクティビティを実施。また、自動運転バスの試乗といったデジタル推進分野も体験いただきました。
開催後のアンケートでは、ワークショップを通じて参加者全員が「今後も地域との取り組みを続けたい、またはこれを機に始めたい」と回答。実際に滞在することでしか分からない感覚や、町民やクリエイター同士のコミュニケーションの意義にもポジティブなコメントが集まりました。
報道関係各位へのご案内・上士幌町やクリエイターへの取材インタビューについても対応をいたします。 ・ニュースリリース添付以外にも、イベントで使用した写真や動画素材のご提供が可能です [ご参考] 滞在中のプログラムや参加者の様子など、ワークショップの詳細をまとめたレポートはこちら |
製品ラインナップ
シリーズ:COLLABORATIONS〈KAMISHIHORO〉
価格:5,000円/㎡ ※税別、送料別
https://whohw.jp/series/collaboration/kamishihoro/
ー グランプリ作品
■製品名 / 品番: Winter dancing / CBKD009
■クリエイター : 福岡未花(ふくおか みか) / デザイナー
【制作コメント】
冬の上士幌町で過ごす中で出会った、さまざまな「キラキラ」をアナログでドローイングしました。雪の輝き、氷に差し込む光、澄んだ空気、白樺の木々から差し込む光など――目の前に広がる風景や、その場の空気ごと閉じ込めるように、感じたままを直感的に描きました。さらに、描いたドローイングを切り貼りしながら再構成し、形や質感を重ねることで、冬の上士幌町で心を揺さぶられた瞬間をできるだけそのまま表現しました。
【審査員による評価コメント】
・頭で考えるものではなく、感じるものだと思うので、目一杯身体を使って表現してくれたことがポイントでした。氷のなかに光が差し込んでいてキラキラしていた、というのはよくよくみないとわからないこと。(graf代表 服部滋樹)
・美しさや色の使い方、光、寒い季節、木、かみしほろを感じます。世界観がとても素敵だと思いました。この後の展開を考えて、町の人たちがみた時に、明るい気持ちになったりかみしほろっていいなって思えたらよいな、という基準で決めさせていただきました。(ワンズプロダクツ 瀬野祥子・瀬野航)
ー 参加者による全ラインナップ
■製品名 / 品番: つもる、かさなる / CBKD010
■クリエイター : 秋元来美(あきもと くるみ)/ 学生
空から舞い降りた雪は、やがて地面を覆い、土に還る。上士幌の歴史や文化も新たな出来事が折り重なり、大地に溶け込むようにして次の時代の礎となったように、雪と歴史の「積もる」現象に着目、時間の重なりや変化を表現した。
■製品名 / 品番: GOOD AIRFLOW / CBKD011
■クリエイター : 市丸蓉(いちまる よう)/ 学生
人との関わりの中でDXの取り組みや、ライドシェアといった風通しの良さや、フィールドワークで感じた風を通して、木々を通る風をモチーフとして町民の明るいエネルギーを描いた。
■製品名 / 品番: Windows / CBKD012
■クリエイター : 佐藤李(さとう すもも)/ 学生
「覗く」という行為を通して見える上士幌の魅力を表現。窓越しの景色をテーマに、写真や図形を用いて構成、上士幌が持つ自然や街の美しさ、そしてその土地ならではの個性を、視覚的に切り取った。
■製品名 / 品番: YUP むすぶ たすけあう / CBKD013
■クリエイター : 中原みお(なかはら みお)/デザイナー
大和言葉「結(ゆ)ふ」につながる語である、「結ふ」は、二つ(以上)のものを結び付けて新たに価値のある何かを造り出すという意味から、上士幌町で見た景色を抽象化して、重ねて柄をつくり上げた。
■製品名 / 品番: Balloon Dots / CBKD015
■クリエイター : みさこみさこ / グラフィックデザイナー
1907年から続く人々の営みによって生まれた格子状の道。その上空に浮かぶ「多様な生き方を尊重し、持続可能なまちづくりを目指す」上士幌町の未来を表現した7色の気球をドットで表現。生活空間に溶け込むパターンをデザインした。
■製品名 / 品番: 痕跡 / CBKD016
■クリエイター : 横田智美(よこた ともみ)/ アーティスト
「上士幌を歩く」をテーマに、実際に歩いた時の感覚を辿るように紙版画を足で踏んで制作。雪に残る痕跡からさまざまな情報が読み取れることを歴史に重ね、今の上士幌の風景を表現した。
ワークショップ開催後の取り組みと今後について
ワークショップ開催後は、2025年3月19日(水)~3月23日(日)に上士幌町「まちのギャラリーhumi」にて、完成したデザイン含め、原画やスケッチ、制作のプロセスを展示。本取り組みを詳細に辿り、広く知っていただく機会となりました。
今後、グランプリ作品は将来建設予定の町役場新庁舎の壁面へ採用予定のほか、ワークショップ参加者による全作品を町の資産として保有。町を象徴するデザインとしてクリアファイル、ポストカード、ステッカーなどの商品化を予定しています。
 写真左・右上:展示会の様子 /右下:前回のグランプリ作品「WINDS AND FIELD」を使用した町のグッズ
写真左・右上:展示会の様子 /右下:前回のグランプリ作品「WINDS AND FIELD」を使用した町のグッズ
「上士幌町」について
自治体名:北海道上士幌町
町役場所在地:〒080-1492 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
HP:https://www.kamishihoro.jp/
北海道十勝管内の北部に位置し、人口5,000人に対して行政面積は約700平方キロメートルを抱え、総面積の約76%を森林が占める緑豊かな町です。基幹産業は畑作、酪農、林業などで特に乳牛の飼育頭数は全国トップクラス。一方、観光に目を向ければ、ぬかびら源泉郷や公共牧場として日本一広いナイタイ高原牧場、北海道遺産にも選定された旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群などが有名です。また、日本で初めて熱気球の大会が開かれた「熱気球のまち」としても知られ、毎年全国から多くのファンが訪れています。
「ねづく」について
2024年4月に設立した一般社団法人ねづくは、北海道上士幌町を拠点に、場や機会の提供により地域の機運を醸成し、新たな風土 が「ねづく」ことを目指して北海道上士幌町を拠点に活動しています。
「WhO(フー)」について
「WhO(フー)」は、より美しく、より愛され、より良い空間を目指し、新しい表現を模索する人のために2015年に立ち上げた壁紙ブランドです。2016年にはグッドデザイン賞を受賞。空間デザイナー目線で制作されたパターンや、多様なフィールドで活躍するクリエイターによるデザイン、プロダクトやサービスなど国内外問わずさまざまなブランド・企業とのコラボレーションから生まれたデザインなど、現在では3,000点を超える個性的で表情豊かなラインナップが揃います。
今後一層拡大するであろう日本のリフォーム・リノベーション市場や、装飾ビジュアル化が進む宿泊施設、店舗・不動産物件などにおいて、より特徴的で美しく空間を彩るデザイン性の高い壁紙に対するニーズに応えます。
国内での完全受注生産によりデザインのカスタマイズにも柔軟に対応。作り手のこだわりに寄り添いながら、在庫を持たず素材のロスを抑え、環境配慮にも繋げています。さらにデジタルカタログの採用により、紙カタログの使用と仮定した場合と比べてCO2排出量の削減にも貢献*¹。室内空間におけるVOCなどの化学物質の排出に関して一定の基準をクリアした「GREENGUARD Gold認証*²」を取得したインクを使用するなど、サステナブルなビジネスモデルを展開しています。 https://whohw.jp/
*¹ 米国のUL Solutions社によって評価された、健康への影響や環境性能を示す認証
https://japan.ul.com/resources/greenguardcertificationprogram/
*² 参照:https://whohw.jp/about/
野原グループについて
野原グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。
社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。

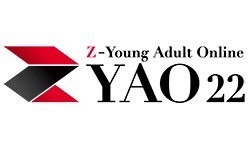













.jpg)
-1.jpg)
_クレジット追加.jpg)
.jpg)




